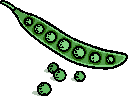| 7月分俳句の添削と寸評 | |
| .. | |
| 今月も相変わらず、私なりの無手勝流の添削と寸評をします。失礼の段は平にお許し | |
| 下さい。いい句が多くなり、うれしく思っています。インターネット句会の欠点を補完する | |
| ために「掲示板」があります。遠慮せずに「掲示板」に投稿してください。そして句会の | |
| 活性化を図っていきましょう。 | |
| . | |
| 番号 | 添 削 & 講 評 |
| 1 | 不折の像青葉若葉の中にかな |
| 「不折の像」がよく分かりません。こういう場合には「まえがき」で具体的に書き添える | |
| 方法があります。「不折の像」で切れますので、「かな」止めはどうかと思います。 | |
| . | |
| 2 | 今生きて明日は朧なカブトエビ |
| 水田の中にカブトエビを見つけたのでしょうか。カブトエビの生きざまに自分を重ねる。 | |
| いい句です。 | |
| . | |
| 3 | 今日も又暑さしのぎの蝉しぐれ |
| 毎日暑い日が続く。暑さを吹き飛ばすように蝉が大声で鳴いている。いい句です。 | |
| . | |
| 4 | 生かされて生く石風呂に汗流し |
| 私の句です。石風呂に汗を流して生きている幸せを噛みしめている。 | |
| . | |
| 5 | プランター移植の苗に簾置く |
| <添削> 簾置く移植の苗を調えて | |
| 「プランター」で切ると、意味が曖昧になります。そこで「プランター」を省略しました。 | |
| これで丁寧に苗を育てている様子が分かると思います。 | |
| . | |
| 6 | 雲海の一角崩れ棚田見ゆ |
| 雲海ですからかなり高い所からの眺めでしょう。雲海の切れ目から棚田が見えてくる。 | |
| 素晴らしい風景です。いい句です。 | |
| . | |
| 7 | マネキンに命吹き込む水着かな |
| 水着を着たマネキンが生き生きとしている。まるで生きているようである。 | |
| 面白い着眼。 | |
| . | |
| 8 | 向日葵や今は盛りの休耕田 |
| <添削> 向日葵の真っ盛りなる休耕田 | |
| 休耕田に向日葵が一杯咲いている。今や観光名所になり、村おこしに一役 | |
| 買っている。美しい風景。 | |
| . | |
| 9 | 微笑みにうなづき返すアマリリス |
| 愛情の眼差しでアマリリスを見詰めていたら、アマリリスが語りかけてくるようである。 | |
| いい句です。 | |
| . | |
| 10 | ラムネ抜く大空仰ぎ音を飲む |
| <添削> ラムネ抜く音の弾ける晴天下 | |
| ラムネ、懐かしいですね。「ラムネ抜く」で切ると意味が曖昧になります。このようにして | |
| みました。ラムネを抜くときの音は快感。 | |
| . | |
| 11 | せせらぎと河鹿の歌のハーモニー |
| <添削> せせらぎと河鹿のハモる晴天下 | |
| 説明的なので、このようにしてみました。 渓流に河鹿がしきりに鳴いている | |
| 情景が伝わってきます。 | |
| 12 | 石畳風に逃げゆく落し文 |
| <添削> 音立てて風に逃げゆく落し文 | |
| 石畳で切るのはどうかと思います。また少し説明的なのでこのようにしてみました。 | |
| . | |
| 13 | 梅雨前線活動はじめ喜雨はじく |
| <添削> 喜羽あがる石鎚山の間近にて | |
| 「梅雨前線「」喜雨」は共に夏の季語です。原句は説明になります。 | |
| . | |
| 14 | 濡縁の傷のあまたやへちま棚 |
| <添削> 濡縁の傷のあまたや蝉しぐれ | |
| 濡れ縁の傷を見てからへちま棚を見ると目移りするという人もいます。俳句は眼前に | |
| ピントを合わせて切り取るものです。そこで物に対して音をもってきました。 | |
| . | |
| 15 | 洗い髪着流しでいる夕涼み |
| <添削> 藍ゆかた着流しでいる無骨者 | |
| 「荒い髪」「夕涼み」は夏の季語です。「洗い髪着流し」は調子が悪いので | |
| このようにしてみました。 | |
| . | |
| 16 | ぼうふらの屈伸運動真似てみる |
| 面白い句ですね。歳を考えて余り無理をしないでください。 | |
| . | |
| 17 | 咲き初め月下の美人夫と待ち |
| <添削> 夫と待つ月下美人の咲き初め | |
| 「月下美人」のことを「月下の美人」とは言をないと思います。 | |
| . | |
| 18 | 征しまま還らぬ兄の終戦日 |
| <添削> 征しまま還らぬ兄や終戦日 | |
| 「兄や」で切ったらどうでしょう。この方が印象が強くなります。優しい兄さんだった | |
| のでしょう。終戦日がくると兄さんのことを思い出します | |
| . | |
| 19 | 土砂降りに声をひそめる雨蛙 |
| 面白い句です。雨蛙も土砂降りには参ったのでしょう。 | |
| . | |
| 20 | 人の道諭すがごとく蝸牛 |
| いい句です。蝸牛は慎重にマイペースで行動をしています。教えられます。 | |
| . | |
| 21 | 水を買うジャンボ田螺の朱の卵 |
| 句意がよく分かりません。悪しからず。 | |
| . | |
| 22 | 国宝の修験道場釣忍 |
| <添削> 峻岳の修験道場釣忍 | |
| <添削> 国宝の修験道場土用照 | |
| 「国宝の修験道場」と「釣忍」と焦点が二つあるので句意が分散されます。 | |
| 焦点を一つに絞って句をつくりましょう。 | |
| . | |
| 23 | 一雨が暑気を払うや夕涼み |
| <添削> 一雨が暑気を払うや屋形舟 | |
| 「暑気を払う」「夕涼み」は共に夏の季語です。 | |
| . | |
| 24 | 無念なりスイカも泳ぐ固め雨 |
| 動物が泳ぐのはいいですが、スイカが泳いではいけませんね。 | |
| 丹精込めたスイカが収穫を間近にしてやられて残念。 | |
| . | |
| 25 | 赤とんぼスイッと飛び去る露天風呂 |
| <添削> 赤とんぼすいと飛び去る露天風呂 | |
| 中八になるので」このようにしました。楽しい旅の景が浮かびます。いい句です。 | |
| . | |
| 26 | ちりりんと涼しげに舞う風鈴かな |
| <添削> ちりりんと舞ふ風鈴の始発駅 | |
| 「涼し」「風鈴」は共に夏の季語です。 | |
| . | |
| 27 | 日傘さし素肌美人の下駄の音 |
| <添削> 小太りの素肌美人の黒日傘 | |
| 「日傘」「美人」「下駄」となると、少し言い過ぎ。このようにしてみました。 | |
| 面白くありませんか。 | |
| . | |
| 28 | 夏の海清新の気に明けわたる |
| <添削> 清新の気に明けわたる夏の海 | |
| 上五を下五にもってきました。清々しい夏の海です。いい句です。 | |
| . | |
| 29 | ひまわりの太陽に向けて諸手上げ |
| <添削> ひまわりの太陽に向く笑顔にて | |
| 中八になっています。調子が悪いのでこのようにしてみました。 | |
| . | |
| 30 | 空梅雨やダムから出る村里や |
| <添削> 空梅雨やダムの底より小学校 | |
| 「や」「や」で切るのはいけません。少し分かりにくいかなと思ってこのように | |
| してみました。子の方が具象性があると思います。 | |
| . | |
| 31 | 城まつり茶髪のギャルも浴衣着て |
| <添削> 浴衣着の茶髪のギャルの大笑い | |
| 「まつり」は夏の季語です「城まつり」も季語になるのではないでしょうか。 | |
| . | |
| 32 | 古びたる机の上に子かまきり |
| <添削> 小机に斧を構える子かまきり | |
| 説明的なので、このようにかまきりの状態を詠んでみました。 | |
| 33 | 北国の友と語りし夏の宵 |
| 「北国の友」がいいですね。「南国」ではつまらない。久しぶりに再会した友と | |
| 遅くまで話しが弾んだことでしょう。いい句です。 | |
| . | |
| 34 | 華道の師夏草花を届けくれ |
| <添削> 生け花の師より届きし透かし百合 | |
| 調子がよくないのでこのようにしてみました。花の名を入れ具象化しました。 | |
| . | |
| 35 | 鳩時計鳴りて原爆記念の日 |
| 私の句です。私は広島の原爆には特別な思いがあります。 | |
| . | |
| 36 | 姉想ふ匂袋の捨てがたし |
| <添削> 姉想ふ匂袋の匂いゐて | |
| このような句もできます。粋なお姉さんだったのでしょう。 | |
| . | |
| 37 | 蝉時雨俄の雨にはたとやみ |
| <添削> 土砂降りにはたと鳴き止む蝉時雨 | |
| 「蝉時雨」を下へもってきました。この方が調子がよくなると思います。 | |
| . | |
| 38 | 遠蛙庭に指揮者のあるごとし |
| <添削> 蛙聞くコンダクターのゐるごとし | |
| 「遠蛙」と「庭」は矛盾しています。 | |
| . | |
| 39 | 空蝉を庭に見つけし梅雨の明け |
| <添削> 空蝉を庭に見つけし二人にて | |
| 「空蝉」「梅雨」は共に夏の季語です。 | |
| . | |
| 40 | 初茄子糠漬けの床調へり |
| <添削> 丹念に糠床作る初茄子 | |
| 「初茄子」で切れ調子が悪いので、下へもってきました。初茄子の浅漬けが | |
| 美味しそう。 | |
| . | |
| 41 | 青田風農夫二人の立話 |
| <添削> 南吹く農夫二人の立話 | |
| 「青田風」と「農夫」は付き過ぎ。季語を替えてみました。世間話をしているのでしょうか。 | |
| . | |
| 42 | 雷雨あり激しい荒れに無事祈る |
| <添削> 雷鳴の過ぎゆく二人目を合わせ | |
| 言い過ぎていますのでこのようにしてみました。 | |
| . | |
| 43 | 雷にパソコンこわされIT絶ち |
| 大変でしたね。くわばらくわばら。 | |
| . | |
| 44 | 父の日に花付きサボテン届きおり |
| <添削> 父の日に届く生花の匂いゐて | |
| 「父の日」「サボテン」は共に夏の季語だす。父の好きな花。 | |
| 優しい子がおられて幸せですね。 | |
| . | |
| 45 | 生い立ちを遙か尋ねしメロンかな |
| <添削> メロン食ぶじっと上目のペルシャ猫 | |
| 誤字があります。原句での「かな」止めはどうかと思います。 | |
| . | |
| 46 | 天仰ぎ一雨ほしい蛙かな |
| <添削>天仰ぎ雨がほしいと雨蛙 | |
| 日照り続きで、蛙も悲鳴をあげている。 | |
| . | |
| 47 | キルトにて表現されし夏景色 |
| <添削> キルトにて色鮮やかな夏の景 | |
| この方が具象性があると思います。 | |
| . | |
| 48 | 子規庵のへちまの棚につるのびて |
| <添削> 子規庵のへちまの花の降りしきり | |
| 「子規庵」と「へちま」は付き過ぎか。 | |
| . | |
| 49 | 御来光待つピッケルを突きさして |
| 私の句です。山頂での御来光は神秘的。 | |
| . | |
| 50 | ピョンピョコと道を横切る雨蛙 |
| 擬声語を使うと俳句は作りやすい。おもしろい句だと思います。 | |
| . | |
| 51 | 山ももの夕映える道岬へと |
| <添削> 山ももの夕日に映える岬道 | |
| 「夕映える」が「山もも」にも「道」にもかかりませんか。 | |
| . | |
| 52 | 梅漬ける指先染る紫蘇の紅 |
| <添削> 梅漬ける指先紅く染りけり | |
| 「梅の実」「紫蘇」は共に夏の季語です。 | |
| . | |
| 53 | 肩ぐるま浴衣の襟を握りしめ |
| <添削> 荒御輿を離れて見つむ肩ぐるま | |
| 上六にしています。原句ですと何を詠みたいのか曖昧。添削句ですと情景がはっきりします。 | |
| . | |
| 54 | カブトエビ乱舞する田や人の果て |
| 人はいなくなったのにカブトエビはしきりに乱舞しているというのでしょうか。 |