
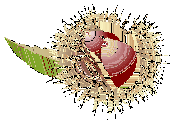
| 10月分 俳 句 の 添 削 と 寸 評 | ||
| 少しはお役に立っているのかと思いながら、非力を省みず私なりの添削と | ||
| 寸評をいたします。失礼の段多々あると思いますがお許しください。 | ||
| . | ||
| 10月は俳句を詠むのにいい季節でした。少しでも沢山作られたのでしょうか | ||
| いい句が多いのでうれしく思っています。何をするにも一歩一歩前進です。 | ||
| . | ||
| 番号 | 披 講 と 添 削 | |
| 1 | 衣更へあたり見回し吾も更へ | 竹 豪 |
| <添削> 衣更あたり見回し吾も更へ | ||
| いい句です。衣更の月になったが、直ちに衣更をするには、 | ||
| 周囲が気になるものです。 | ||
| そして少々勇気がいります。人間の心理をうまく表現されています。 | ||
| 「衣更へ」は「衣更」としました。 | ||
| . | ||
| 2 | 日の暮れを稲木に預け子らかへる | 峰 生 |
| 私には句の意味がよく分かりません。悪しからず。 | ||
| . | ||
| 3 | 秋うらら遠方よりの荷が届き | 初 霜 |
| いい句です。一人暮らしの母からの贈り物か、母が丹念に作った野菜も | ||
| 沢山はいっている。いつまでたっても親心。ありがたいことである。 | ||
| . | ||
| 4 | 畦道に大空仰ぐ捨案山子 | 哲 朗 |
| いい句です。今年はお陰様で豊作。畦道にお役目の終わった案山子が | ||
| 捨てられている。大往生である。 | ||
| . | ||
| 5 | 大屋根に大屋根の影鳥渡る | 彰 子 |
| 私の句です。西山興隆寺での句です。大屋根に大屋根の影が | ||
| 動いていく。おもしろい景を発見。折しも鳥が群れをなして渡ってくる。 | ||
| . | ||
| 6 | 秋の灯や幼き頃のなつかしさ | 泉 |
| いい句です。秋の灯に幼き頃を思い出しているのです。 | ||
| 秋は郷愁にかられるものです。 | ||
| . | ||
| 7 | 能登の海おだやかなりし秋日和 | 浩 風 |
| いい句です。晩秋から冬にかけて日本海は荒れる日が多くなります。 | ||
| しかし今日はすばらしい秋日和。絶景の能登の海を満喫する。 | ||
| . | ||
| 8 | 木せいの香にふと止まる散歩道 | 峰 生 |
| <添削> 木犀の香にふと止まる散歩道 | ||
| いい句です。木犀の甘い香りにしばらく佇み感傷にふける。 | ||
| 「木せい」を「木犀」にしました。 | ||
| . | ||
| 9 | 座り地蔵苔濃き衣薄紅葉 | 媛 香 |
| 調子が悪く読みづらい。何を詠みたいのか今ひとつよく分かりません。 | ||
| 考えてみてください。 | ||
| . | ||
| 10 | やさしかな心の痛み酔芙蓉 | 泉 |
| 「やさしかな」の使い方は私にはよく分かりません。考えてみてください。 | ||
| . | ||
| 11 | 打ち下ろす碁盤に響きに秋の声 | 蝋 梅 |
| <添削> 碁石打つ音の冴えゐる集会所 | ||
| 私には何を詠みたいのか今ひとつよく分かりません。中八になって | ||
| います。上手く添削できませんが、このような句を作りました。 | ||
| . | ||
| 12 | 祭りきて子等のかけ声町わたる | 泉 |
| <添削> 新調の子供御輿を高く上げ | ||
| 原句では焦点があいまいで説明になります。 | ||
| . | ||
| 13 | こおろぎやころころラブを歌い居り | 蝋 梅 |
| <添削> こおろぎやころころころと歌いをり | ||
| 「ラブ」と言わない方が余韻があると思います。 | ||
| . | ||
| 14 | 天高く竿竹売りの声響かせ | 菜の花 |
| <添削> 天高し竿竹売りの朗々と | ||
| 「声響かせ」は六音になります。 | ||
| . | ||
| 15 | 栗の毬割けて三つ子が顔を出す | 千 柳 |
| いい句です。栗は二つ子や三つ子が多いのでしょうか。つやつやした | ||
| 元気そうな栗の顔。 | ||
| . | ||
| 16 | 栗を剥く三児の母となりし娘と | 楓 花 |
| いい句です。少子が問題になっているとき三児の母とは素晴らしい | ||
| ことです。幸せな暖かい家庭が伺えます。 | ||
| . | ||
| 17 | 秋空に祝詞静かに吸ひ込まれ | 千 柳 |
| いい句です。七五三の朗々たる神官の祝詞が澄み切った青空に吸い | ||
| 込まれるよう。爽やかな清々しひととき。 | ||
| . | ||
| 18 | 朝寒や樟脳臭ふ服を着る | いなご |
| <添削> 秋澄むや樟脳臭ふ服を着る | ||
| いい句です。「朝寒や」「樟脳臭ふ服を着る」では少し付き過ぎ | ||
| かなと思いましたので、このような句にしてみました。 | ||
| . | ||
| 19 | 赤まんじゅ白曼珠あぜの競演 | そらまめ |
| <添削> 曼珠沙華燃ゆ一片の雲を置き | ||
| 原句は言い過ぎになります。特に「競演」は避けましょう。 | ||
| . | ||
| 20 | 秋晴れや新築の屋根葺きあがる | コスモス |
| いい句です。平凡な句のようですが、情景がよく分かります。秋天下に | ||
| 白銀の屋根瓦がきらきら輝いていて、新鮮な生き生きした気分になる。 | ||
| . | ||
| 21 | 団栗を供える童かしこまる | いなご |
| <添削> かしこまり子ら団栗を供えゐる | ||
| 調子が今一つですので、前五と下五を入れ替えこのようにしてみました。 | ||
| 子供の真剣な様子が伝わってきます。 | ||
| . | ||
| 22 | 湯煙に太鼓の響き紅葉映ゆ | ゆづき |
| <添削> 湯煙に太鼓の響く秋気かな | ||
| 「湯煙」「太鼓」「紅葉」は物が多すぎます。省略しましょう。 | ||
| 添削句では「紅葉」を省略しました。 | ||
| . | ||
| 23 | 秋時雨他国を忍ぶ千里ケ浜 | 石の花 |
| 私には句意がよく分かりません。悪しからず。 | ||
| . | ||
| 24 | 喜寿すぎてダンス楽しむ枯芒 | ゆづき |
| <添削> 喜寿すぎてダンス楽しむ鰯雲 | ||
| 喜寿すぎてダンスを楽しむという羨ましい人生。ますますお元気で。 | ||
| 「枯芒」は替えましょう。 | ||
| . | ||
| 25 | 結婚式チャペルの鐘に秋茜 | 哲 朗 |
| <添削> 式告げるチャペルの鐘に秋茜 | ||
| 三段切れになるのでこのようにしてみました。結婚を祝福するように | ||
| 秋茜が映える美しい光景です。おめでとうございます。 | ||
| . | ||
| 26 | 秋祭り中張の声幼くて | 初 霜 |
| 「中張の声」というとどんな声なのでしょう。 | ||
| . | ||
| 27 | 千枚田作る人無き秋時雨 | 石の花 |
| <添削> 千枚田荒れるるままや秋時雨 | ||
| 後継者がいないので千枚田は荒れ放題。先祖から営々と伝えられてきた | ||
| 素晴らしい素晴らしい田園風景、いつまでも残したいものです。 | ||
| . | ||
| 28 | 秋祭り告げる太鼓のリハ−サル | 竹 豪 |
| いい句です。秋祭りが近づくと町が活気づき、太鼓の音に気分が弾む。 | ||
| . | ||
| 29 | 草むしる土の匂ひや秋の風 | 蝋 梅 |
| いい句です。庭の草をむしるのは大変な作業ですが、 | ||
| 自然の営みを肌に感じ心が安らぐ。 | ||
| . | ||
| 30 | 名月よ投句日せまり助けてよ | そらまめ |
| 弱音を言わないで。誰も助けてはくれません。自助努力あるのみ。 | ||
| . | ||
| 31 | 旧姓の飛び交ふ秋夜同窓会 | 風 花 |
| <添削> ゆく秋や旧姓飛び交ふクラス会 | ||
| 調子が悪いのでこのように詠んでみました。中八ですが許される | ||
| と思います。 | ||
| . | ||
| 32 | 抛りあげてどんぐりころばす城の道 | コスモス |
| <添削> どんぐりを放れば転ぶ城の道 | ||
| 上6、中8です。五七五に整えてみました。 | ||
| . | ||
| 33 | 老境となりぬ小鳥の来てゐたり | 彰 子 |
| 私の句です。近頃年をとったことをしみじみ感じ行く末が気になります。 | ||
| 小鳥に慰められています。 | ||
| . | ||
| 34 | 切り子山車能登の祭りをうねり行く | 石の花 |
| 賑やかな祭りなのでしょう。「切子山車」といったものをよく知りません。 | ||
| 関係無いかと思いますが、「切子」または「切子灯籠」は秋の季語に | ||
| なっています。 | ||
| . | ||
| 35 | 雀居て鳩も来たりし刈田かな | いなご |
| <添削> 大刈田なる雀ゐて鳩もゐて | ||
| のどかな田園風景。共存の自然界。 | ||
| . | ||
| 36 | 仕舞いてより早きを悔いる残暑かな | コスモス |
| <添削> 早仕舞して悔やまれる残暑かな | ||
| いつまでも残暑が厳しいので夏物を早く仕舞ったことを悔いていると | ||
| いう、状況は良く分かります。上六になるのでこのようにしてみました。 | ||
| . | ||
| 37 | 菜園に飛行機の舞う天高し | そらまめ |
| 「菜園に飛行機が舞う」というのは模型飛行機のことでしょうか。 | ||
| 景がよく分かりません。また、「飛行機」と「天高し」は付きすぎです。 | ||
| . | ||
| 38 | 石鎚山人の写真で紅葉狩り | 菜の花 |
| <添削> 石鎚山(いしづち)に人いっぱいの紅葉狩 | ||
| 俳句は眼前の感動を物に託して詠むものです。 | ||
| . | ||
| 39 | 秋雨にひとりたゝずむ恋路浜 | 浩 風 |
| いい句です。恋路浜と言う固有名詞がいいですね。ロマンチック。 | ||
| . | ||
| 40 | 提灯の火を消し秋の祭り果つ | 初 霜 |
| いい句です。町内での最後の灯でしょうか。明るかった町が暗くなり、 | ||
| 賑やかだった祭りも終わったことを実感する。 | ||
| . | ||
| 41 | 夕暮れや方言飛び交う芋煮会 | さつき |
| いい句です。「夕暮れや」と言う詠嘆の強い切れはどうでしょうか。 | ||
| . | ||
| 42 | あすなろの一葉いたゞく秋うらら | 浩 風 |
| <添削> あすなろの一葉いただく秋うらら | ||
| いい句です。思いがけないところに着眼されたところが手柄です。 | ||
| . | ||
| 43 | 遊歩道丸木の椅子に夕暮れや | 媛 香 |
| <添削> 萩こぼる丸太ん棒の遊歩道 | ||
| 調子が悪いのでこのようにしてみました。 | ||
| . | ||
| 44 | 今一度見上げて眠る後の月 | 風 花 |
| いい句です。後の月をいつまでも惜しむ。明日もいい月夜であって | ||
| ほしいと願う。 | ||
| . | ||
| 45 | 振り向けば見渡すかぎり鰯雲 | さつき |
| いい句です。農作業が終わり背伸びをすると大空いっぱいに鰯雲が | ||
| ひろがっている、明日もいい天気のようである。また頑張ろう。 | ||
| . | ||
| 46 | ひつじ田に群れ来る雀猫が追う | 哲 朗 |
| <添削> ひつじ田に雀の群るるよき日和 | ||
| 情景は面白いのですが、「ひつじ田」「雀」「猫」と物が多すぎる | ||
| ように思います。 | ||
| . | ||
| 47 | 蠅叩き名人の名を妻にあげ | 竹 豪 |
| 詩情に欠けます。考えてみてください。 | ||
| . | ||
| 48 | 冴え返る瞑想に没頭阿弥陀堂 | 媛 香 |
| <添削> 秋澄むや瞑想深かむ阿弥陀堂 | ||
| 中九になっています。「冴え返る」は春の季語です。春の季語を使って | ||
| も悪くはないのですが、秋の季語にもいい季語が沢山あります。 | ||
| . | ||
| 49 | 朝明けやメルヘン浮かべうろこ雲 | 峰 生 |
| <添削> 朝明けのメルヘン調のうろこ雲 | ||
| 「メルヘン浮かべ」という言い方があるのでしょうか?「うろこ雲」 | ||
| を強調するため上五の強い切れ字はやめて軽く切りました。 | ||
| . | ||
| 50 | どことなくモクセイの匂い爽やかに | 菜の花 |
| <添削> どことなく木犀匂ふ日暮時 | ||
| 「木犀」「爽やか」はどちらも秋の季語です。中八になっています。 | ||
| . | ||
| 51 | その昔モミジだったと手を翳(かざ)す | 千 柳 |
| <添削> その昔紅葉だったと手を翳(かざ)す | ||
| いい句です。発想が素晴らしい。「紅葉」は漢字がいいのか、 | ||
| ひらがながいいのか? | ||
| . | ||
| 52 | 曼珠沙華燃ゆる剣豪生誕地 | 彰 子 |
| 私の句です。宮本武蔵の生誕地に曼珠沙華があかあかと燃えている。 | ||
| . | ||
| 53 | 坪庭の夕餉に添える秋茗荷 | さつき |
| いい句です。小さいが手入れの行き届いた庭での夕餉。 | ||
| 「秋茗荷」が効いている。 | ||
| . | ||
| 54 | 半世紀よくぞ耐えたり日向ぼこ | ゆづき |
| 「一世紀」とは西暦で、100年を1単位として数えます。したがって | ||
| 「半世紀」とは50年を意味すると思います。50年はまだ若い。 | ||